|
|
|
|
|
| ◆成果主義的人事改革の実相 - 鉄道関連 |
|
1.問題意識-鉄道事業の公共性と成果主義
90年代後半以降、いわゆる成果主義が問題になってきた。これに関する研究や報告も近年、多くなってきている。既にそうした議論は飽和状態にあり、意義を失ったという声もある。いずれにしても、そこで交わされる議論はややもすると拡散的で、実相の見えにくいものが少なくない。多くの議論は抽象度が高く、現状を正しく捉えるというよりも、今後のあり方を理想として、あるいはあるべき論として提言していくというものが多く、そのためか、現状の問題の所在、あるいは現状把握そのものが議論からは見えにくくなっているように思われる 。そこで、これらの論議を整理しつつ、人事改革として起こっている実際の成果主義がいかなるものなのかを事例の中で確認したい。
鉄道は電気やガスなどと並んで、我々にとって必須の公共的インフラである。また鉄道とその付帯関連事業のもたらす雇用は量的にも莫大であり、その意味でも無視できない重要な存在と言えるだろう。今回取り上げた事例は、関西の私鉄T社及びその関連会社C社だが、鉄道本体だけでもその従業員は数万人であり、主な関連事業である百貨店、外食産業、駅構内の売店だけでもそれぞれ1万人を超える従業員数を抱えている 。関西私鉄系企業グループは主要5社だけで約50万人の雇用を抱えている(阪急、阪神、南海、近鉄、南海の5社)。これは近畿6県の雇用者数(835万人、2006年3月現在)の6%にも及んでいる。
鉄道が安全で安心できる乗り物であってほしいという希望は社会的に強い要請としてある。しかしながら、JR西日本における事故(2005年4月25日)などその信頼を揺るがす出来事も起こっている。そこで、鉄道事業及びその付帯関連事業における人事管理の実態を、事例を通じてなるべく実情として検討し、その背景で起こっている「人事改革」の諸相について考察したい。人事改革の裏側で起こっている賃下げ、非正規化、非正規雇用における雇用の融解と劣化などが果たして社会的インフラを支えうるのか、疑問も湧いてくる 。また競争優位を実現するための成果主義人事がいかに雇用を破壊してしまうのか、たとえ仄見える程度であっても、その実相に迫ってみたい。
2.成果主義に関する議論とその意義
成果主義に関しては交わされる議論は少なくはないので、最近の論議を大まかに概観し、整理しておく必要がある。『日本労働研究雑誌』は成果主義に関して2006年9月号(No.554)で特集号を組んでいる。この中で、山本紳也氏は、成果主義導入後の15年を、①手つかずの時代(1991年~1995年)、②気づきの時代(1996年~2000年)、③再生の時代(2001年~2005年)、④真のスタートへの時代(2006年~)の4つのステージに分けている。成果主義への取り組みは企業によって異なるが、何らかの諸段階があることには異論がない。また成果主義的人事改革の中身が企業によって異なるのはむしろ当然のことかもしれない。ただ、人事改革に取り組む時期は企業にとって異なり、単純に数年の刻みで指し示すことには無理があるように思われる 。また成果主義が時代の流れとする見方は果たして企業自身にとって好ましいことなのか、疑問がある。
日本企業への成果主義の導入は能力主義からの移行であったとする見解がある。例えば、今野浩一郎氏は、80年代の能力主義賃金を「供給重視の賃金制度」と表現している(「供給者側本位の賃金制度」と言えばわかりやすいと思う)。この点を石田光男氏は踏まえた上で、右肩上がりの市場環境の下で企業が保有する賃金コストを市場が吸収してくれることを暗黙の前提として当時の賃金制度が組み立てられていたが、90年代以降の賃金改革、すなわち成果主義的人事改革は、そうした楽観論を捨て去り、「市場を取りに行く」改革でなければならないとする 。今野の表現で言えば「需要重視の賃金制度」ということになるかもしれない(「供給者側本位ではなく供給者である企業が受け身になる賃金制度」と言えようか)。これらの観方は雇用を安易に犠牲にする企業姿勢を市場原理として肯定する表現であり、今野氏や石田氏のスコープにはすぐさま傅けない部分がある。
このような流れ、すなわち供給者側本位ではなくなるという流れの中で、「人(の生活)」を基準とする人事制度から「職務」あるいは「仕事」を基準とする人事制度へと切り替える展開がなされている 。言い換えると、人の生活を基準とし、その生活を保障するというスタンスから、人(の生活)に関わりなく、その仕事内容によってなるべく安い労働力を買うというスタンスがより明確化されてきている。このことは中野(2006)によって「労働ダンピング」という言葉を用いて議論されている。また能力主義と成果主義が対比して捉えることにはそれなりの意義があるだろう 。
阿部正浩氏によれば、「成果主義」にも問題が存在するにもかかわらず、日本企業でそれが普及してきた背景には、「労務費の高騰」という経営問題だけでなく、技術進歩やコーポレート・ガバナンスが変化してきたことも関係している。そこには「能力主義」が破綻したという積極的な理由はあまりなかったのではないかと指摘されている 。確かに、成果主義は能力主義を当初は温存してその適用範囲を縮小し、周辺部分を拡張することによって組織の環境適応を促進してきたという面がある。少なくとも、能力主義が180度転換したという捉え方はできないかもしれない。ただ、この部分の議論は成果主義の捉え方ないし定義によって右にも左にも行くものかもしれない。
成果主義についてはその捉え方がややもすると拡散しているとする指摘がある 。これは「能力主義が制度としての収斂が高かった」ことと比較すると、特徴的だとされている 。確かに、成果主義では職能資格制度のような統合的な人事制度はない。むしろそれを瓦解させる取り組みが多いように思われる。それでも、成果主義には、ノルマ管理を重視した目標管理の推進や、ストレッチした目標設定や職務行動の実行を促進するコンピテンシーが一定の役割を果たしており、人事・賃金制度の再構築に寄与している 。そこには統合的な人事システムはないにせよ、特有の人事管理の運用がある。事例を通じて考えるべき点だろう 。
成果主義の導入ではいくつか有名な事例がある。1つには富士通である。城繁幸氏によれば、成果主義として導入されたものとして、①部門ごとの目標作成とブレークダウン、②評価結果の賞与額および昇給額への反映、③裁量労働制への移行などがその内容であったという 。言い換えれば、目標管理を強化し、結果重視の処遇管理とし、時間外手当を削減することによって賃金パフォーマンスを向上させる取り組みだった。また評価方法は絶対評価から相対評価に切り換えられ、評価段階ごとの分布調整がなされたことがあるという指摘もある。しかし、目標管理にしても、コンピテンシーにしても、その評価の考え方は絶対評価である。相対評価を重視するということは、そうした絶対評価による一次評価はあくまでも参考にして、人物や業績などで序列付けを行ない、原資に配分を重視するようになったことを意味する 。
また成果主義に関して、武田薬品工業の事例が有名である。同社ではヘイグループに莫大なコンサルティング・フィーを払って成果主義人事制度を導入したことで有名である。アカウンタビリティが重視され、一種の職務給が採用され、コンピテンシーを使ったアセスメントが導入されたと喧伝されている。評価方法は相対評価ではなく、絶対評価である。武田のケースは成功事例としてしばしば紹介されている 。確かに武田の事例は人事改革が1997年から開始されたことを鑑みれば成果主義に関して他社に先駆けるものかもしれない 。しかし、何がどう成功したのか、誰にとっての「成功」なのか、いまひとつ見えてこない。武田が「人事改革」を目指したと同時に、労働組合と何らの相談もなく、10年以内に従業員を半分にして大再編を行なうと発表したことがある 。武田における成果主義人事改革は人員削減のための具体的なプロセスだったのではないだろうか。
2000年以降に導入された成果主義は「格差の小さい」マイルドな成果主義で、その原因は「後発効果」と「プロセス重視の結果」で、「コンピテンシーを重視した」ものという指摘がある 。しかし、この点について、城繁幸氏は、現場に導入される評価の仕組みがややこしく、実際には相対評価で推し進められていくことを指摘している 。こうした学識者の指摘は必ずしも企業の実情と一致するわけではない。成果主義の流れに遅れた企業の賃金改革が格差において小さいこともあるが、それは実務雑誌などで示された賃金テーブルのピッチの違いであり、実際にどのように分布しているかは外部には見えにくい。90年代後半、企業は当初、格差の大きい処遇を強調したが、実際の評価処遇はそのように大きなものにはならなかった。また後発企業もしくは先進企業が後にコンピテンシーによって補正されたという指摘もあまり適当ではない。なぜなら、コンピテンシーへの注目とその導入は「米国型」人事管理への同化を図ることであり、成果主義とは本来、直接関係がないからである 。成果主義をやるなら、コンピテンシーを導入するのは必然的であるという議論も聞かれないし、成果主義を是正するのにコンピテンシーが意味を持つという論議もあまり一般的ではない。
同様の調査を数社で実施したが、それによると、外資系製薬会社F社でも、日系食品会社N社でも、人事部に上がってくる情報は相対評価であり、絶対評価の仕組みは現場の能力開発の指標もしくは参考資料に留められていた 。そもそも絶対評価と相対評価は厳然と切り分けられるのだろうか。企業は絶対評価を看板にするが、両者は並存しているのかもしれない 。またF社では例年、業績連動型の報酬管理が行なわれているが、コンピテンシーとは関係がない。N社ではコンピテンシーを導入していない。
成果主義について守島基弘氏は、「成果」と「処遇」の後工程のみが重視され、「人材育成」や「配置管理」が軽視されてきた、これではモチベーションが上がらないと指摘する 。確かに、個人単位での成果を重視すると、部下や後輩を育成する精神的な余裕がなくなってくるかもしれない 。しかし、配置管理に関して成果主義の前と後で特段の変化はなかったし、それらは別次元である。成果主義が推進されれば、どのような仕事に配置されるかはより関心事になってくるだろう 。なぜなら、それによってその担当で成果が出せるかどうかが違ってくるからである。また人件費を抑制する動機を強く持つ成果主義では、モチベーションは犠牲にしてもよいという発想がある。組織行動論の痛切で人事部は組織デザインを考えているわけではない。
成果主義によってメンタルヘルス上の問題が生じてくることも無視できない。荒井千暁氏は、キュブラー・ロスの『死ぬ瞬間』という本で、死に至る人間の心理的プロセスを、否認、怒り、取引、抑うつ、受容としていることを模倣して、成果主義を受容するプロセスを次のように説明している。当初は「受容」であり、「まぁ、低成長の時代だから仕方がないなぁ」という時期がある。その後、報酬が上がらないことに「当惑」し、「なぜこうした評価になるのか?」、「低い評価を受けているのは私だけなのか?」と困惑する。さらにその後は「再調整」の段階になり、評価結果が納得できないので、「評価基準を明確化してくれ」という要求が出てくる。ところが、相変わらず処遇が改善されず、まずまずの評価のはずが標準評価になり、手応えありと本人が思ってもマイナス評価になってくると、「不信」の段階になる。この頃になってくると、組織体は一気に危うくなってくる。その後は「絶望」、「混迷」の段階に至る。そうなると、組織体のみならず、同僚などに対しても絶望感が生じ、「もうやってられない」という感情が巻き起こってくる。この段階になると、キャリアアップを求めるわけでもなく、より多くの報酬を求めるわけでもなく、離職していくことになる 。成果主義は組織を荒廃させ、一方で正社員のメンタルヘルスを悪化させ、その一方で若者の離職者を増大させている 。
成果主義に関する議論を概観してきたが、いずれも正規雇用のゾーンに位置する従業員のみを問題にした議論で、時に人事制度に関する論議に偏しているように思われる。しかも、その論議は多く、企業の表向きの制度改革の広報を鵜呑みにしている。しかし、今日、非正規雇用で働く労働者は雇用者全体の3分の1以上を占め、実際の組織を見ても、8割ないし9割が非正規雇用者であることが珍しくなくなっている 。現在あるような論議からは日本企業の実態というものが見えにくいことを指摘しておきたい。
3.鉄道関連会社における人事改革-その概要と諸相
(1) 会社及びグループ企業の概要
事例のC社は、関西地区に位置する私鉄の関連会社で、駅構内の売店や、駅付近のベーカリー、小売店(雑貨店)、コンビニエンス、食品スーパーなどを運営している。兄弟会社にはD社があり、この会社は沿線および鉄道本体が所有する不動産(建物、土地)にレストラン(和食や洋食、中華など)などの外食事業を展開し、経営している。C社の従業員規模は正社員約700名、パート社員3500名であり、圧倒的にパートの比率が高い(パート比率84%)。しかも、パートのほとんどが女性で、女性比率の極めて高い構成になっている(パートの女性比率99%)。パートで男性は学生アルバイトだけで、全体の1%にも満たない。なお、会社の年商など経営成績について企業の特定化を防ぐために伏せておきたい。
なお、C社あるいはD社のような企業は私鉄関連会社では必ずと言っていいほど実在する(各社とも「リテールサービス」や「観光」と付く)。例えば、駅員は現在、各社とも関連会社からの駅構内への派遣であり、鉄道本体に属することは基本的にない。T社の場合、2003年時点でゼロになっている。このような派遣会社を関西私鉄各社は「ステーション・サービス」と呼んでいる。関連会社を設置する目的は移籍によるリストラであり、こうした移籍は雇用条件の改変(=改悪)のために悪用、濫用されている面を否定できない。
事例のT社では元運転手や元車掌を大量に移籍させているが、その移籍率は2003年時点で全体の4割以上に及び、現在も移籍を計画的に推進している状況にある。鉄道本体に収益力がなく、「支えきれない」というのがその理由である。現在も、C社には200名ほどの鉄道従業員が出向しているが、賃金は基本的に本体が負担しており、その人事評価も鉄道が行なっている。この200名はC社従業員数にカウントされていない。その移籍は数年以内のことと予測されている。
(2) 人事改革までの経緯
C社は2000年にD社から事業の一部を営業譲受し、その際、200名弱の正社員の移籍を受け入れた。D社の従業員は一旦、D社を退職し、退職金を受け取り、その後、C社に雇用される形を取った。しかし、2004年時点では昇給や正式な格付けをしていなかった。そのため、「人事改革」を行ない、人事制度の一本化を行なう必要性が生じた。ところが、3期にわたって昇給手続きが行なわれず、賞与のみで調整されてきたために、C社の賃金分布はかなり歪んでしまった。具体的には、年功的な傾斜を急にしてしまっていた。賃金分布を図に描くと、金額にして3万弱、年額にして50万程度、勾配が急になった(図1)。若年層は低く抑えられ、中高年はその基本給の多さによってより多く年間報酬を受け取る形になっていた。この乖離を放置したまま、昇給させてもその差は広がるばかりである。しかし、経営層も人事部もその変化には気付いていなかった。
【図1】
|
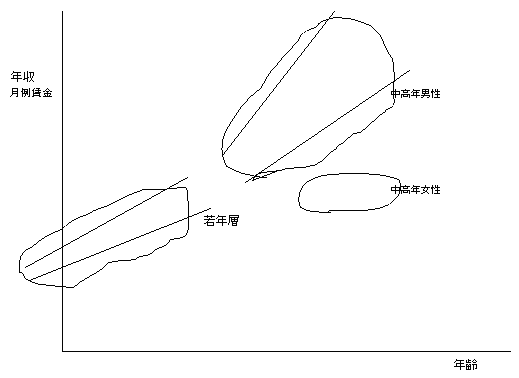 |
ここに言う3万弱とは、一方の平均年齢32歳と、もう一方の平均年齢48歳の代表的賃金の格差のことを指しているが、その比較は賃金モデルを策定し、検討した(主な年齢での実在者の実際の数値を拾い出し、軌跡として結んだ)。若年層における代表的な賃金カーブは関西の100-300名規模の製造業平均よりもやや低い水準で推移していたが、中高年層はこの3年も順調に昇給してきていたので、500名規模以上の賃金指標の水準であった。統計は各種用意したが、入手しやすいものを採用した(関西経営者協会)。企業規模を考えると、若年層の水準は月例賃金でも年収実績でも低かった。
なお、営業譲渡の際、格付けや基本給の決定は3年以内に行なうとしていたので、制度の整備と各社員の落とし込みが必要になっていた。そこで、外部委託して制度構築をし、評価制度の整備、賃金制度の運用を考えることになった。
(3) 人事改革の内容と実際
人事改革と言えば、今日、成果主義ということになるかもしれない。しかし、C社で検討された人事改革は必ずしも成果主義という性格を持つものではなかった。少なくとも、過剰な年功主義、平等主義は排除すべき、またその是正をすべき、あるいは理想であるべき同一労働同一賃金に少しでも近づけようと当初は考えられたが、それ以上踏み込んだ改革に向けての発想は基本的になかった。さりとて、新人事制度を「能力主義的な制度」とするにはもはや時代遅れという腹積もりがあった。そこで、出てきた方針は次のようなものだった。
先ず、労基法にもあるような、同一職務同一賃金原則の可能な限りの尊重、これまでほとんど顧みられることのなかったパート社員の処遇改善、である。次に、若年者層と中高年層の賃金ギャップを埋めること、の2点である。また適切な評価制度を整備し、業績や成果および行動や態度を評価し、処遇に反映することである。こうした方針を持ちつつも、実際の改訂作業に入っていくと、思うように方針が実現しないこともある。実際には次のような施策が取られることになった。
《具体的施策》
A) 従来あった資格等級体系を全廃し、ゼロベースで職能資格制度を構築し、そこに各社員を格付けするようにした。その際、簡便ながら職務分析を実施し、仕事の難易度が職能給(この会社では「仕事給」)に反映するようにした。従来の「仕事給」の等級格差には何の意味もなく、にもかかわらず大きな格差があった。等級格差は縮小された。また同一等級内の習熟昇給は小さく抑えた。特に上位等級での習熟昇給は抑え込んだ 。しかし、それでも、同一等級の範囲給の範囲は広く、何年もかけて是正していくか、格下げを行なわないと整合性がないというもののまま移行せざるを得なかった。
B) 格付けに際しては各人の仕事内容や責任範囲、指示のされ方、指示命令の範囲などを重視した。実際に担当している仕事と等級が対応するように配慮した。しかし、そうしたやり方では本来位置づけられるべき等級に収まらない実在者が何人か出てきた。それは次のような社員だった。
① 仕事内容はパート社員と全く同じで、販売職なのだが、社員としての勤続年数の非常に長い人。いずれも女性社員で、年収600万円をやや超えていた。新制度によれば、その年収水準は400万円を上回ることはないと想定された。話し合い、急に引き下げられないという結果に落ち着き、賞与などで徐々に調整していくことになった。賃下げについては保留。
② 現業部門で人望の厚い男性社員。一人だけなのだが、水準が非常に高かった。新制度における「販売・物流職」では1等級および2等級に格付けすることになっていたが、2等級の範囲給では収まらない水準だった。やむなく3等級に格付けした。本人の仕事内容に関してヒアリングを行なったが、部下はなく、監督職的役割はなかった。賃下げについては保留。
C) 従来の評価制度では、欠勤や有給休暇取得に対してペナルティを課すほかは平等的なものだったが、これでは労基法の精神からも問題が多い。この点は、業績(仕事そのものの成果)と行動(観察された職務行動や態度)という評価観点が新たに構築され、導入された。従来は、人事考課について業績と行動を分けて行なうという習慣がなかった。総合的に決定されるので、欠勤すると、能力が低いとみなされ、昇格対象ではなくなるという実情もあった。その点では改善され、人事考課を行なうという制度が初めて導入された 。
D) 若年層については是正が必要となった。同一企業としてのバランスもあったが、現状では適切な新卒の初任給さえ設定できない水準だった。全体のバランスを考え、一人当たり2万以上の特別昇給が実施された。最高で4万昇給した実在者もあった。そのための原資は経営側も許した。改訂原資に2.5%程度を要した。
E) パート社員の処遇改善はなされず、正社員の処遇調整のために、パート社員に年に2回支給されていた賞与が廃止された。パートへの賞与は一人当たり数万円だったが、人数も多いので、賞与を廃止すると、昇給原資を賄うのに寄与するところが大きかった(総額で8000万円程度、一人当たり2万3千円程度、時給換算で20円程度)。パートの賞与制度は廃止され、今後採用していく際、時給を上げていくことになった。ただし、昇給ルールも雇い入れの改訂が明確化されたわけでもない。パートの時給は10円上げるだけでも年額4200万円になる(10円×1200時間×3500人)。比較的採用の難しい地域などに限定しても、数千万円の改訂原資がかかり、実際には難しい問題がある(例えば、100円×1200時間×500人=6千万円)。しかし、求人媒体に出しても応募がほとんどないこともあり、是正は不可避になっている 。
F) 全体としては、4%程度の改訂原資を要し、これを執行した(実額約15.6億円、正社員人件費総額390億円)。成果主義人事改革が推進される時期の賃金制度見直しの原資としてはこの率自体は破格のものと思われる。改訂原資がマイナスの賃金改定も多いからである。パートの賞与は正社員の平均年収(550万円)で割り返すと、2.1%程度になり、正社員若年層の改訂原資に消えてしまったというのが正確かもしれない。ただし、人事部は立場上、そういう見解には立っていない。
(4) 問題点と事例から明らかになった諸点
今回の事例を通じて次のようなことが明らかになった。要点を列挙し、問題点を検討したい。
《鉄道関連会社における諸問題》
A) 鉄道会社は不動産関連への過大な投資などにより経営難に陥っている。またバブル崩壊後の長引く不況で、沿線における販売などの付帯事業も業績不振が続いており、人件費原資もなく、人事リストラを余儀なくされている。関西私鉄では次のような施策が急速に進んでいる。
① 正規社員に対する退職勧奨 特に車掌、駅員。特に自己都合退職をじわじわと迫るもので、その意味で悪質と言えるかもしれない。
② 車掌のパート・アルバイト化への置き換え H社では時給800円~(年収150万程度) 表1参照。
【表1】年齢別雇用形態別の時給及び年収概算
|
| |
年齢 |
労働時間 |
時給 |
年収概算 |
| 正規中高年 |
55 |
1,500 |
6,000 |
9,000,000 |
| 正規若年層 |
30 |
3,600 |
5,400,000 |
| 非 正 規 |
25 |
800 |
1,200,000 |
|
|
※ 車掌の労働時間は比較的短い。
※ 非正規の車掌に関しては1500時間を越えることはない。
③ 駅員の別会社からの派遣への切り替え 駅員は本体の従業員ではない。例えば、「Kステーション・サービス」などの呼称。移籍時に賃下げされている。移籍は賃下げのみならず、退職金を清算することで将来の労働債務を小さくする効果がある。退職金は通常、自己都合だと支給係数が低くなり、また勤続年数が20年、25、30年という節目で高くなる。鉄道各社は高卒で雇った社員のうち、40歳代以上の運転手、車掌を対象に、自己都合で退職するように働き続けてきた。少なく見積もっても、退職金による労働債務の削減効果は関西私鉄5社合計で2000億円相当になる(一人2000万円平均で対象者1万人)。
B) 労働組合は本来、会社と対等な立場に立ち、会社が行なおうとする人事改革、制度改定を監視し、適切に対処するよう、全社的な立場で提案することが本来望まれているものと考える。しかしながら、労働組合の構成員は正社員のみであり、パート社員の利害を代表するものではない。また圧倒的多数が男性であり、資格等級の上位層を占めるのは男性で管理職一歩手前の層である。また実際の労組はどんなものか。50歳を過ぎて管理職にならないなど年配の社員に発言権が強く、彼らの発言は意固地で、自己中心的であり、若年者の利害を無視することに往々にして多い。C社でも社長よりも高齢の社員が自分たちの給与を上げよと強く要求があり、人事部も困惑した。結果的に、中高年社員の報酬を据え置くことが精一杯の抵抗になった。それだけでも、数ヶ月にわたる話し合いが続いた。
C) 伝統的企業といえども、人事考課制度の整備は意外に遅れている。形の上では構成されていても、実際には欠勤や有給休暇の消化について厳罰を科すなどが実態で、ワーク・ライフ・バランスを取りにくい実情がある。正社員であっても、女性が育児しながら働くという状況にないことも現実である。人事担当からも社員に関して「遅くまで残って頑張っている」という発言が時々出てきた。休日出勤をいとわないことを評価しようとする声も依然として強い。
D) 今回の事例、C社の場合、成果主義的な改革と言っても、それが前面に出るものではなく、若年層への特別昇給が許される一方で、人事制度の枠組みに乗らない実在者の賃下げは見送られた。実は賃下げ、格下げをうまく行なわない限り、人事改革は整合しない。結果的に職務分析に基づく公正処遇という観点からは違和感の大きい人もそのままレールに乗せ続けることになった。C社では中高年社員(おおむね50歳代を中心とし、45-58歳の実在者)の報酬を引き下げることも検討したが、反対が強く、実現しなかった。成果主義的な制度の運用は今後の課題であるが、毎年抵抗に遭うことは目に見えている。このようにも捉えられるが、貢献度の高い人に厚く報いるだけの原資が実際にはなかったので、モデル賃金を大幅に超えるようなスター社員を作ることも困難だった。制度に乗りにくい実在者の異動や解雇なども検討したが、現状までの貢献度が大きいので、そういう方向で行くことは納得性を欠いた。そうした判断を招いたのは企業自身に、仕事の内容で評価する、想定される職務基準で評価し、処遇する発想がなかったとも言える。
4.全体的考察と今後の展望
事例として取り上げたC社は人事制度改訂としてそれを見るとき、典型的な成果主義人事改革とは言えない。成果主義的人事改革の事例は、おおむね次のようなものであると考える。すなわち、①人件費総額を圧迫する経営上の困難があり、能力主義的な人事制度運用に限界が来て、同一資格等級内での習熟昇給を抑制する。その一方で、それに対する批判を交わすために一部の者だけを大きく昇給させる。②平均値としての昇給を大幅に押さえ込み、降給の仕組みを織り込んで、賃金テーブルとその運用を見直す。例えば、上位等級の賞急ピッチを削減したり、シングルレートにしたりする。③厳しい評価を下すことへの批判をかわすために、評価制度をより綿密化する。こうした改訂が一般的な成果主義で行なわれることである。これに対して、C社の場合、①の状況にはなかった。また②についてもまだ十分実施段階にないが、賃金設計には織り込んでいる。③については多少取り組みつつある。全体として、制度をとりあえず整備する改訂であった。ただ、特徴的と言えば、非正規従業員を犠牲にして、特別昇給が行なわれたことである。
成果主義的な人事改革については新自由主義との関連で捉える論議がある(小越、2000など)。言い換えるならば、「成果主義は、競争環境に対応するために行なわれる人事と組織の改革」と言うことになるかもしれない。しかし、言い方はどうであれ、H社の車掌の事例にあるように、そもそも競争優位を得るとか、明確なビジョンを伴って事業戦略があって行なわれていることではないことも忘れてはならない。本来、年功賃金として保証し、生涯にわたる雇用と共に清算をつけていかなくていけなかったところを、成果主義は態度を急変して打ち止めにしようとしているものである。そもそも企業の経営状態が悪化してくれば、その賃金は多少なりとも下がってしまうのは当然である。人員削減も行なわれるかもしれない。そうしたことが当然であり、仕方がない部分もあるからこそ、春闘のような場を持ち、長年、話し合いも行なわれてきたのだと思う。しかし、H社の車掌の事例で数字を当てはめて考えてみると、どうだろうか。実際にはありえないが、高卒のフリーターが車掌を40年間従事してもその生涯年収は4800万円程度で、5千万円にも満たない。現在、50歳代の実在者で試算すると、生涯年収は2億5千万円程度で、退職金や福利厚生などを組み入れると3億円程度になる。その格差は6倍にもなる。経営状況が悪いから、賃率を6分の1にすることは合意の上のことなのか。仮に話し合いがあればそうした極端な申し入れは円満裏に折り合いがつくのだろうか。
成果主義を考える際、事例で見たように非正規化が急速に進んでおり、正規雇用の常用代替によって企業が人件費を押さえ込んでいる実情を見逃してはならない。また労働組合が成果主義による人事改革を行なっても、あまり強い抵抗を示さないこと、まして女性労働や非正規雇用に目配りした提言を行なうことがほとんどないことも注意しなければならない。非正規雇用に見られるような流動性の高い人材群に関しては、従来の労使関係で構成してきたようなフレームワークでは見えにくい部分があるように思われる。女性や非正規の処遇改善に関しては労組にあまり期待できないように思われる。その一方で、C社の事例で見てきたように、正規雇用のゾーンにある人たちの制度改訂はあまりにもソフトランディングなのである。
参考文献
阿部正浩「成果主義導入の背景とその功罪」『日本労働研究雑誌』No.554 2006年9月
荒井千暁『職場はなぜ壊れるのか―産業医が見た人間関係の病理―』ちくま書房 2007年2月
今村寛治「成果主義の実相―能力から仕事へ―」日本労務学会・労務理論学会合同九州部会2006年12月27日配布資料
風間直樹『雇用融解』(東洋経済新報社)2007年
楠田丘『人を活かす人材評価』(経営書院)2006年
小越洋之助『終身雇用と年功賃金の転換』ミネルヴァ書房 2006年1月
小越洋之助他『今日の賃金 財界の戦略と矛盾』(新日本出版社)2000年
中野麻美『労働ダンピング』(岩波新書)2006年11月
城繁幸『内側から見た富士通-「成果主義」の失敗』光文社 2004年
城繁幸『若者はなぜ3年で辞めるのか?』(光文社新書)2006年9月
立道信吾、守島基弘「働く人からみた成果主義」『日本労働研究雑誌』No.554 2006年9月
柳下公一『わかりやすい人事が会社を変える-「成果主義」導入・成功の法則』日本経済新聞社 2001年
柳下公一『ここが違う!「勝ち組」企業の成果主義』日本経済新聞社 2003年
|
|
|
|
|