|
|
|
|
|
| ◆コンピテンシーを人事管理にどう活かすか ~コンピテンシー礼賛論は危険な罠となる~ |
|
1.問題意識
組織の成員の職務能力に関しては比較的確立された評価基準として、アセスメント・センターの「ディメンション(dimension)」がある。しかし、コンピテンシーが日本で流行するようになり、次第にあまり違和感なくコンピテンシーと言い換える例も出てきた。またヒューマン・アセスメントで有名な機関のひとつである、米国DDI社もヒューマン・アセスメントの際にその基準としてコンピテンシー(competency)を使うようになった。一方、米国PDI社はスキル・ディメンション(Skill Dimension)という用語を採用している。なお、本稿では、評定基準を「行動ディメンション(Behavioral Dimension)」と呼んでいる。
どのような概念規定を行なうにしても、何らかの分析を行い、職務能力の類型を再構成できないものだろうか。なぜなら、それによって、行動ディメンションを再構成することが可能になるからである。そこで、本研究では、サービス業の管理者に対して行なったアセスメント・センターから得られたデータを分析し、行動ディメンションの再構成の可能性を探った。
なお、最初にコンピテンシーという用語を使う以上、これに関する論議について少し言及しておきたい。
2.コンピテンシーに関する悩ましい状況
コンピテンシーとは一般に「高業績者の行動特性」ないし「高業績者が職務行動を優位化する要因」と考えられている。コンピテンシーに関しては一時的な流行りに過ぎないとか、そもそもそのような概念設定すら危ういという指摘もある。一方で、コンピテンシーを学習するという観点を重視すべきだという見解があり(古川、2002)、少なくとも近年の日本の組織行動論においては主流な立場となりつつある。しかし、このような理解は日本的なものであり、多少とも交通整理しておく必要がある。概ね次のように考えることができるだろう。
まず、米国の文献をサーベイする限り 、また2003年時点において北米の実務家や有識者の意見を聞く限り、北米では実務的にはコンピテンシーはあまり重要な概念と考えられていない。Hullの指摘するところによれば、コンピテンシーを処遇決定の基礎とする運用をしている例は1つもない、という。またSchnooverの行なった調査によると、コンピテンシーを処遇決定の基準に使った例はほとんどなく、活用している場合もその満足度は低いという 。コンピテンシーの活用は主に採用選考であり、コンピテンシーに関する実務書は採用選考(recruitment and selection)のものである。Lawlerはコンピテンシーを脆弱な基盤に過ぎないと断じている(Lawler,1996)。そうしたコンピテンシーに関するネガティブな評価があるにもかかわらず、日本の人事実務の中で評価手法ないし育成手段としてコンピテンシーが肥大化していることは明らかに不均衡だと言わざるを得ない 。そのため、近年ではコンピテンシーを単に「行動評価」と言い換えたり、「行動指標」とする例も出てきている 。
一方で、学術的にはそもそもこのような概念を認めること自体、いろいろな意味で困難が生じてくるという意見も少なくないようだ。渡辺直登氏によれば、「コンピテンシーは職務分析の1つの手法以上のものではないと米国では捉えられている」指摘する 。また「コンピテンシーという概念はいずれかと言うと結果変数であり、ここから接近することを認めてしまうと、原因変数からパフォーマンスを捉え、分析しようとする組織行動の多くの試みの前提が危うくなってしまう」 としている。確かに、コンピテンシー(competency)という概念は産業・組織心理学や組織行動論の標準的なテキストにはあまり取り上げられてこなかった 。大きな論点にはなっているとは考えにくい。しかし、「コンピテンシー・モデリング(competency modeling)」ということで多少とも触れられるようになってきた 。しかし、こうした研究は依然としてマイナーであり、リーダーシップやモチベーション、キャリア発達などのように、組織行動論で大きくクローズアップされる論点ではない。
3.調査方法
本研究では、サービス業(本社:東京都千代田区、従業員約5000名、うち正社員約900名)の管理職及び管理職候補を対象に、2年間にわたりアセスメント・センターを実施し、そこから得られたデータを分析した。対象者は250名ほどだが、締め切った時点でのサンプル数は115名である。彼らは同社の管理職の一部であるが、その約8割が店舗の責任者である。男女構成では約1割が女性である(男性103名、女性12名)。
アセスメント・センターとは、グループ討議(Group Discussion)、面接演習(Interview Simulation)、インバスケット演習(In-basket Simulation)、プレゼンテーション(Analysis Presentation)などを行い、それらの演習を複数のアセッサーが観察記録し、アセッサー会議で言動に関する統合を行い、評定するものである。米国で発達した、この手法は、1970年代以降、日本にも紹介され、各社で導入されている。なお、各演習では、表1のような課題を与えた。また評定に当たっては、表2にあるような行動ディメンション一覧の着眼点を常に念頭に置き、観察された言動を該当する行動ディメンションに照らし合わせ、その強みと弱みを評価した。
演習は2日間の日程で実施し、1回のワークショップに15名程度の受講者を参加させ、アセッサーとして3名、さらに演習をサポートするスタッフ2名が加わった。演習を実施するに当たっては標準化された手順でガイドが行なわれ、演習を実施し、アセッサーはこの言動をきめ細かく観察・記録し、各演習終了後に行なわれる会議で情報を共有化し、研修日程最後に開催される統合会議で評定を行なった。演習は2005年から定期的に実施され、2007年5月時点で累計8回となっているが、今後も100-150名程度の管理者のアセスメント実施が予定されている。
【表1】 演習の概要
|
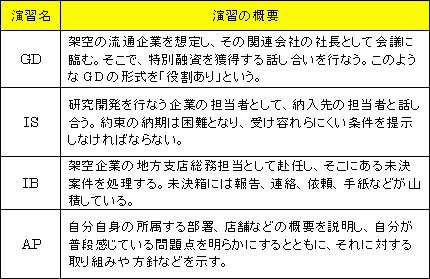 |
4.調査結果
アセスメント・センターから得られたデータを集計したが、まず男女別に集計をまとめ、その後、データを因子分析した。聴き取りによって実在者の背景(仕事内容や社内での考課状況など)を確認した。ただし、それらの情報を織り込んだデータ分析は保留した。アセスメントはまだ全体の半分程度であり、階層別、職務内容別で集計するには十分でないからである。
(1) 男女別の集計結果
行動ディメンションごとの評点を単純合計すると、48(16×3)になるが、男女別の平均値を見ると、男性が46.2に対して、女性は49.5であり、女性管理者(管理者候補を含む)の能力が平均して高いことがわかった。全体での平均は46.5だった。女性受検者で平均点48を下回る者はいなかった。
(2) 人事考課との整合性
人事担当者からの聴き取りでアセスメント・センターの結果が概ね人事考課の結果と整合していることが確認された。とりわけ、上司に持っている部下のプロフィールとほぼ一致していることが確認された。ただし、アセスメントで低得点層の実在者にも人事考課で高い得点の者が含まれていた。数人の実在者について確認を取ったところ、少なくとも上長からの人物評価が高いということがわかった。一方、アセスメントで評価の高い人について平均的な人事考課の得点しか得られていないケースもあった。それについては在社年数が短い、事業所のイメージが希薄で本人の存在感がないなどの指摘があった。また現職務での適性が十分でない可能性もあるのではないかという意見もあった。
5.討論と展望
コンピテンシー・モデリングの方法としては聴き取り(行動インタビュー)によって高業績者が体験的に述べた職務行動から特徴的と思われる事項を項目化してモデルにしていくというのが最も普及したやり方で、そうした方法をSpencer(1993)も、アセスメント・センターに代わる簡便法として紹介している。しかし、短時間のインタビューで掘り出せる優位的行動はそう多くないし、網羅的でもない。これに対して、アセスメント・センターは想定された15-18程度のディメンションに関して繰り返し観察された言動を拾い出すことができ、対象者の能力構造を、その人の中で強弱として捉えると同時に、まとまった集団の中で強弱をつけて評価することができる。つまり、個人の中での強弱、集団の中での相対評価、設定された基準から評定した絶対評価が同時に可能になる。そのデータからコンピテンシー・モデリングを行なうことは一定の意味を持っていると考える。
ただ、設計された演習からでは見えない部分も多い。表○では、アセスメント演習では見えにくいが、企業が把握しておきたい行動ディメンションの例を挙げておいた。
【表2】 アセスメント演習では見えにくい行動ディメンション
O 戦略的思考力 (置かれている状況にある機会と脅威を認識し、対応策を打ち出す)
O キャリア展望 (5年後ないし10年後の自分自身のキャリアを認識し、やるべきことを自覚している)
O チームワーク力 (組織にあるチーム意識を敏感に察知し、それを効果的に引き出す)
O 組織との一体感 (所属する企業、部署の一員としての意識を持ち、一体感を持っている)
O 定着志向性 (多少不満なことがあっても、今後とも所属している企業で働く意識を持っている)
O 離職志向性 (近い将来、この会社から辞めて離脱してしまうことを考えている)
O 経営感覚 (管理職層であっても、経営者としての意識や見方を持っている)
O 問題意識 (日頃から瑣末なことから全体的なことを考える意識を持っている)
O コスト意識 (コストを削減し、あるいは投入されているコストが効果的になるように意識している)
アセスメント・センターから得られる結果は人事情報として評価されている。人事考課との整合性が高く、人事考課のブレを補完し、修正するという意味で参考になっている。また本人に育成的なフィードバックを行なう際、本人にも納得されやすいプロフィールが描けていることが必要になるが、その意味ではアセスメントの描くプロフィールは示唆的である。
またアセスメントの結果を単純に総合点で捉えるのではなく、意思決定系、対人影響系、個人特性系という3つの系統で捉え、配属や異動の際の参考にしている。この企業の場合、店舗では必ずしも高い意思決定系の能力は求められてないようで、対人影響系及び個人特性系の能力のうち、対人感受性、コミュニケーション力、自律一貫性などが職務適性に関連していると考えられている。これに対して、本部企画系の仕事は意思決定系の能力について要求水準が高い。ただ、この点に関してはまだ十分な検討が加えられたわけではない。また系統化は統計分析によって裏付けられなくてはいけない。
今後、アセスメントを全社的に行なう必要がある。サンプル数を十分に確保した上で、担当職務(店舗、本部企画系、本部サポート系など)と考課段階(5段階)とを関連付け、重回帰分析などの手法で分析する必要がある。すなわち、担当職務別の考課段階を従属変数にし、16ディメンションを独立変数にして確認してみる必要がある。そうすることによって職務成功に寄与する行動ディメンションが明らかになってくる。ただし、現状では全員の人事考課結果の開示を受けてデータ提供されているわけではない。これは今後の課題になるだろう。
また女性のアセスメント結果が高いことについてはいろいろな解釈ができるし、今後の対応策として考えるべき点も少なくない。考慮すべきことはこの企業の女性が属している職域や階層、労働環境である。女性の店舗責任者はまだ少なく、まだ登用は十分とは言えない。女性の平均勤続年数はまだ長くはないし、部下を抱えて管理者として活躍している実在者もまだ多くない。女性の離職率が高いことはこの企業に限らず、確かに問題になっているが、企業自身にも問題はある。優秀な人材を確保するためには新卒、中途採用などで女性の採用数を増やし、女性比率を高めていくことが求められている。ただ、この企業の場合、22時以降の深夜労働、土日にまたがる勤務があることなどワークライフバランスが取りにくいという問題も抱えている。就業管理を工夫し、有能な女性を登用する人事管理の仕組みを考えていかなくてはならないだろう。
アセスメント・センターのディメンション因子構造に関してはこれまでにも分析が加えられてきた。例えば、外島(2001)によれば、398名の管理者に対して行なったアセスメントの結果を分析したところ(反復主因子法、ヴァリマックス回転)、3つの因子が得られた。それはそれぞれ、「問題把握」、「自立的決定」、「効果的な働きかけ」と命名されている。なお、GD(グループ討議)の形式は「役割なし」となっている。
本研究と外島(2001)との因子構造の差は、GDの形式が「役割あり」か「役割なし」かによるところが大きいと考える。役割のないGDの討議題材の場合、発言機会を逸してしまい、単に頷いたり、迎合したり、同調するだけになってしまう受講者が出てきやすい。そうなると彼らはイニシアティブ、能動性、自律一貫性などにおいて低く評価されやすく、意思決定系の能力もポジティブには評価されにくい。一方、発言機会の多い受講者の評価はイニシアティブ、能動性、自律一貫性、問題分析力など幅広く高く評価されてしまう。その結果、外島の研究では第2因子に「自立的決定」が登場し、決断力、コントロール(管理統制力)、自主独立性(自律一貫性)、バイタリティ(能動性)がその因子となったと考える。また各演習の難易度がどのようなものかにも影響される。とりわけ、IB(インバスケット演習)の課題の難易度は意思決定系の行動ディメンションの評価を左右する。
また筆者(2005)では、因子構造は、第1因子が「問題把握」、第2因子が「対人影響」で、第3因子以降は因子解として明確化できなかった(主因子法、ヴァリマックス回転)。あえて言えば、第3因子は「タフネス」、第4因子は「責務感」だった。このときのサンプル数は39名と少なく、分析に限界があったと考えることができよう。このサンプル数は同じ会社でその後、115名まで増やすことができた。今後、200名を超える段階で、階層と職域に分けて因子構造を探る機会を持つことができる。女性のサンプルが多くなれば、性別での分析を行なっていく必要がある。また新入社員を除く幅広い層にアセスメントを実施すること、再受講の機会を設けることも検討されている
。
もとより、ディメンションの因子構造は、その抽出法、対象となった階層、職種などによって異なっている。今回の対象企業以外の企業でアセスメントを継続的に行なったところ、若手社員(概ね27-32歳の社員)と初級管理職(38-42歳の新任管理職)でかなり異なる結果が得られた(主因子法、ヴァリマックス回転)。3つ程度の因子構造という点では差がないが、若手では「熱意のこもった働きかけ」、「課題の把握と対処」、「責務感」となり、一方、新任課長代理では「粘り強さと胆力」、「課題の把握と対処」、「コミュニケーション」となった。なお、職種別、男女別には明らかにされてない。
いずれにしても、このような因子構造を明らかにすることで、その階層、職種、男女別でどのような行動ディメンションを軸にしてパフォーマンスを発揮しているのか、逆にどのような行動ディメンションの不足や欠落でパフォーマンスを発揮できないのか、を明らかにすることができよう。またそれによって今後採用していく人材像や、育成していく方向、職種や階層によって異なる期待像が明確になってくるものと考えられる。
ただ、アセスメント・センターのディメンション因子構造の分析という捉え方では、因子が3つないし4つ程度に収束してしまい、このようなものだけでは人事考課の基準にすること、育成のためのフィードバック基準にすることは十分とは言えない。本来、能力評価の基準は人事考課の基準の一部と一致していることが従業員の納得感を得やすいように思われる。ただし、人事考課は仕事そのもの、あるいは仕事の成果にも着目する。成績や業績という側面は能力評価と別に必要になってくるだろう。また対象者の能力を把握するだけではなく、育成のための話し合いに資する概念設定が必要になる。これはどこかで基準作り、指標作りを目指さなくてはならない。
今後の課題として残された点も少なくない。近年、パワハラ、すなわち上司や同僚によるいじめが問題になっている。こうした組織阻害行動(counter-productive behavior)は人事考課でも考慮されなくてはならない。このような行動にはそれ相応の背景があると考えられ、別途追究していかなくてはならない。しかし、アセスメント・センターの枠組みでは捉えにくいし、コンピテンシー・モデリングにも織り込みにくい。とはいえ、何らかの組織における行動倫理基準と仕組み作りを考えていかなくてはならない。
主要参考文献
Berman, A. Jeffery Competence-Based Employment interviewing Quorum Books 1997
Boyatzis, Richard The Competent Manager: A Model for Effective Performance Wiley-Interscience 1982
Briscoe, J. P. & Hall, D. T. Grooming and Picking Leaders Using Competency Frameworks: Do They Work? An Alternative approach and New guidelines to practice Organizational Dynamics, 1999 Autumn, 37-52.
Goleman, Daniel Emotional Intelligence Bantam Dell Pub Group 1997
Goleman, Daniel and Boyatzis,Richard Primal Leadership: Learning to Lead With Emotional Intelligence Harvard Business School Pr 2004
Grote,Dick The Complete Guide to Performance Appraisal AMACOM 1996
Hofrichter, David A. and Spencer, Lyle M., Jr. Competencies: The Right Foundation for Effective Human Resources Management. Compensation & Benefits Review.21-24 November-December, 1996.
Lawler, Edward E., III. Competencies: A Poor Foundation for the New Pay. Compensation & Benefits Review. November-December, 20ff 1996.
Lawler , Edward E., III Rewarding Excellence: Pay Strategies for the New Economy Jossey-Bass Inc Pub 2000
Lepsinger, Richard and Anntoinette D. Lucia. The Art and Science of 360 Degree Feedback. Pfeiffer/ Jossey-Bass Inc., San Francisco, 1997.
McClelland, David C Testing for competence rather than 'intelligence, American Psychologist, vol. 28, 1973, pp.1-14.
Pfau, Bruce et al. The Human Capital Edge: 21 People Management Practices Your Company Must Implement (Or Avoid) to Maximize Shareholder Value McGraw-Hill 2001
Schippmann,J.S.,Ash,R.A.,Battisa,M.,Carr,L.,Eyde,L.D.,&Sanchez,J.I.(2000).The practice of competency modeling. Personnel Psychology, 53,703-740
Spencer, Lyle et al. Competence at Work: Models for Superior Performance John Wiley & Sons Inc 1993年3月 邦訳 ライル・スペンサー他、梅津祐良他訳『コンピテンシー・マネジメントの展開―導入・構築・活用』2001年12月
Schuster, J.R., and P.K. Zingheim. The New Pay: Linking Employee and Organizational Performance. New York: Lexington Books. 1992.
The Hay Group: Thomas P. Flannery, David A. Hofrichter and Paul E. Platten People, Performance,& Pay Free Press 1996
Schoonover,Stephan http://www.schoonover.com/ 調査は2000年。
Smith,P.C.,& Kendall,L.M. Retranslation of expectations: An approach to the construction of unambiguous anchors for rating scales Journal of Applied Psychology , 47 149-155 1963
Whetzell,D.L. and Wheaton,G.R. Applied Measurement methods in industrial Psychology Davies-Black Publishing 1997
Wood, Robert and Payne, Tim Competency Based Recruitment and Selection A Practical Guide Willey 1998
Zemke,Rom. Job competencies: Can they help you design better training? Traing 19(5), pp28-31. 1982 May
Zingheim, Patricia Does One size fit all? ACA journal 1996 Spring
玄田有史『仕事のなかの曖昧な不安―揺れる若年の現在』中央公論新社 2001年12月
ヘイコンサルティンググループ『正しいコンピテンシーの使い方―人が活きる、会社が変わる!』PHP研究所 2001年11月
一條和生「知識創造時代のリーダーシップ」リクルートワークス所収 2000年2月
石井脩二『知識創造型の人材育成シリーズ・人的資源を活かせるか』中央経済社 2003年6月
太田隆次「報酬制度にみる米国・欧州企業のコンピテンシー-に対する関心」リクルートワークス所収 2000年2月
太田隆次『コンピテンシー-アメリカを救った人事革命』経営書院 1999年7月
太田隆次「コンピテンシーと職能資格制度の接近から生まれるもの」『ワークス33号日本的雇用システムの未来デザイン』所収 1999年4月
金井壽宏・高橋潔(2004)『組織行動の考え方』(東洋経済)
楠田 丘『人を活かす人材評価制度』 経営書院 2006年9月
佐藤純『コンピテンシー・ディクショナリー 第2刷』社会経済生産性本部生産性労働情報センター 2005年5月
外島裕(2001)「アセスメントセンターのディメンション因子構造とパーソナリティ特性」日本性格心理学会大会論文集No.10(20010827) pp. 58-59 日本パーソナリティ心理学会
本間正人『適材適所の法則 コンピテンシー・モデルを越えて』PHP出版 2005年5月
パトリシア・ベナー『ベナー看護論―達人ナースの卓越性とパワー』医学書院 1992年1月
古川久敬『コンピテンシー・ラーニング―業績向上につながる能力開発の新指標』日本能率協会マネジメントセンター 2002年2月
日詰慎一郎「自己効力理論によるコンピテンシーの実証研究―地方自治体Aで働く係長のキャリア支援に向けて―」日本労務学会誌第7巻第2号 2005年10月
南隆男(1996)「キャリア発達の課題」三隅二不二・山田雄一・南隆男編『組織の行動科学』(福村出版)所収
元寺大志『コンピテンシー・マネジメント』日本経団連出版 2000年7月
ワークス57号『コンピテンシーとは、何だったのか?』2003年4月
|
|
|
|
|